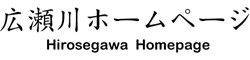■ サクラマスという河川のシンボル
サクラマスの回遊行動は、多くの点で特徴的です。例えばシロサケが秋の産卵期直前に河川に進入するのに対して、サクラマスはそれより早い冬から春にかけて川に入ってきます。そして中流域で越夏し、秋に上流域の産卵場にその姿を現します。およそ数ヶ月間、シロサケとさほど変わらぬ大きな魚体を淵や深瀬に潜ませているのです。私達は、サクラマスの回遊行動を生理学的観点から研究しており、その結果、サクラマスでは性成熟の進行に伴って卵巣や精巣などの生殖腺から分泌される性ホルモンが一種の生理的仕掛けとなって、海から川、川の下流から上流への産卵遡上行動が順次、適切なタイミングで引き起こされることが明らかになってきました。このことから、サクラマスの回遊行動が完成するためには、その川の途中に下流から上流への移動を阻む障害が少ないことがとても重要だと考えられます。

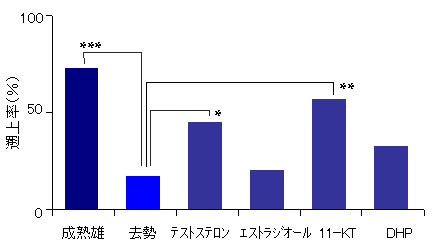
■ サクラマスなどのサケ科魚類が河川の生態系にもたらすもの
このように回遊性魚類の視点から見ると、河川とは、切り取った一部の流域のことではなく、上流から中流、そして河口へと続く、流れ全体のことだということが分かります。そして良好な河川環境が成立した時のシンボルの一つとして、サクラマスという魚があると思うのです。
また、別な視点から見ると、サクラマスなどのサケ科魚類は河川の生態系を豊かにする栄養分の運び手でもあると考えられています。彼らは自分の子孫を残すために故郷の川に戻ってきます。しかしその一方で産卵を終えた亡骸は、そこに暮らす微生物や藻類、水生昆虫類の養分となり、ひいては翌春に浮上する稚魚や多くの川魚に豊富なエサを供給する、食物連鎖の出発点になるのです。従ってサケ科魚類などの回遊性魚類に配慮した川づくりが今後さらに推進されれば、広瀬川全体の生態系は今よりも数段豊かになり、それは他の河川づくりにとっても先駆的なモデルとなることが期待されます。

おわりに
私たちは現在も広瀬川に対して多くのインパクトを与えています。ゴミ投棄や河川構造の問題があり、また水資源の過剰な消費による流量の低下や水温上昇の問題にも直面しています。しかし今こそ私たちはこれらの課題を克服し、サクラマスをはじめとする多くの魚類が暮らす広瀬川が環境都市仙台のシンボルとなるように、新しい時代に向かって進んでいかなければならないと強く思っています。