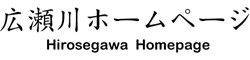フリーライター/西大立目祥子
大橋たもとにあった木場

■田園にとけこむように流れる広瀬川下流
取材で一度お会いしただけなのに、表情や話しぶりが目に浮かんで、ぜひもう一度話を聞きたいと思う人がいるものだ。
上愛子にお住まいの岡本与惣治さん(昭和7年生まれ)も、そんな方だった。会ったのはもう7、8年前。父親の留吉さんが広瀬川の水を利用して薪を流した大倉流木の最後の親方だったと聞き、訪ねたのだった。
岡本与惣治さん

木流しをご存知だろうか。山深いところで伐採した木を、川の流れを使って下流へ送ることをいう。(この広瀬川HPに「広瀬川研究レポート」として仙台市歴史民俗資料館の佐藤雅也さんが記しておられるので、詳しくはそちらをお読みいただきたい。)
大倉流木は、明治30年代から昭和10年代まで広瀬川上流の大倉の木を伐採して広瀬川に流し、大橋の左岸、ちょうど市民プールのあったあたりで引き上げるという事業を行っていた会社だった。流木は薪として、一般家庭や軍隊、商家や工場などに販売された。
「木を伐り出したのは定義の奥。夏に伐って、雪解けの季節に一気に流したんだったよ。水量はいまよりずっと多かったからね。大橋の木場まで、1週間で1000棚(1棚は5尺四方)は流せた、と親父がいってたな」。
岡本さんは、幼い頃に眺めた風景と父親の話をつないで昔語りをしたあと、子ども時代に親しんだ鳴合峡へ案内してくれた。“鳴合の七つ石”とよばれる巨岩が並ぶところだ。「あれはクラカケ石、あれはタタミ石…」と指さす岡本さんは、河原で一段とにこやかでくつろいだ表情になった。
昨年の12月末、久し振りに訪ねると、岡本さんは変わらない口ぶりで、再び木流しの話をしてくださった。
「定義の奥にはブナ林があって、ブナだとかミズナラを伐り出して長さを切りそろえ、定義の角岩から流したんだ。ひと抱えもあるようなのは割って、小口にはみな赤いペンキで印をつけた。水に漬かる時間が長いと木は沈んでしまう。この辺の人は川に薪の流木を拾いに行ったもんだったが、印のあるものは返さなければならなかったんだよ」。
茶の間には、「最後の流木親方」と記された父親の留吉さんの写真が飾ってある。お元気だったら107歳になるという。
岡本留吉さんの写真
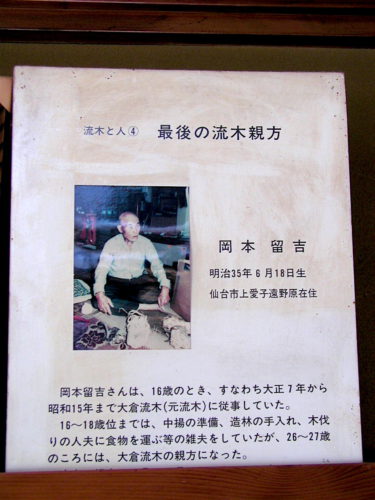
「面倒見のいいやさしい人だった。奥さんに何いわれたって言い返すこともなくてなあ」と、与惣治さんの奥さんのとよ子さんが話す。
「んでも、仕事は鬼だったんでねえの。伐り出してから木揚げするまでが親方の仕事。木流しの季節は家に帰ってこなかったね。流したあとは、泳ぎの達者な若いの連れて川の際を歩いて、引っ掛かっている木は流させる。泊まりながら下ったんだ。まあ、いまならさせられねえ危険な仕事だな」。
60年前に消えた木流しの仕事が、父親の思い出としていまだ語りつがれていることに、温かいものを感じた。
留吉さんは流木の仕事から離れたあとも、山の仕事を続けたという。米寿のときには歩いて月山に登り、3日間だけ床に伏して94歳で亡くなった。