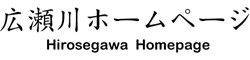フリーライター/西大立目祥子
米ヶ袋の河原で草を食む乳牛

米ヶ袋にお住まいの三原征郎さんがおもしろい写真を見せてくださった。霊屋橋を背景に乳牛が草を食み、その向こうにはマンションとアンテナがそびえ立っている。ビルと牛が同じフレームにおさまっているのに驚いた。写真の裏には、昭和45年(1970)10月と記されている。
「米ヶ袋下丁にあった今野牧場の牛だよ。よく河原で放牧していたからね」と三原さん。もう一枚の写真には、向山の崖を背景に柵で囲まれた放牧場と、「低温殺菌 今野牧場」と看板を掲げる小屋が写っている。三原さんによれば、ちょうど宮城県工業高校のわきに、昭和40年代後半まで牧場があったらしい。牧場経営をなさっていた今野さんのお住まいを教えていただいて、訪ねてみることにした。
■広瀬川沿いにあった最後の牧場「今野牧場」
米ヶ袋の今野牧場

うれしいことに今野さんのお住まいの前には、まるで目印のように写真の小屋がまだ立っていた。写真と同一のものではないが、白く塗りつぶされた看板がかかり、その下には「今野牧場」の文字が透かし見える。今野牧場の創業は明治36年(1903)。初めは、いまの県工のところで牛を飼いながら野菜もつくる、いわゆる多角経営をしていたという。
3代目にあたる今野明さんが、さっそく放牧の話をしてくださった。「毎年5月から10月頃まで、牛を河原に放したもんです。朝、搾乳が終わると河原に連れて行くんですよ。上流は花壇の自動車学校あたりまで、下流は宮沢橋の上、ボート屋があったあたりまで、県から権利を買ってね。評定河原にも放したねえ。このぐらい草が生えてれば3日は大丈夫、これなら1週間は持つ…そんなふうに、河原を見ながら予定立てて歩いたもんです」。
牛の道を案内してくださる今野明さん

米ヶ袋なら、牛を牧場から直接河原に下ろせたが、花壇や評定河原となるとそうもいかず、2人がかりで20頭ほどの牛を、米ヶ袋を抜け、片平丁小学校の前を通って河原へと引いていった。のっそりのっそり、白黒まだらの大きなホルスタインが、まちの中をいくようすはどんなだったか。「車にクラクション鳴らされると、横道に入ったり、走るのもいたんです」。当時を思い出す今野さんの表情が柔らかくなる。
「愛宕さん(愛宕神社)の下に放牧するときは、牛に川を渡らせたね。牛は水は怖がらないの。深いところは、首だけ出して泳ぐんです。運動させると、乳の出方が違うんだねえ。そういえば、牛が河原でお産したこともあったな」と、今野さん。広瀬川の下町段丘に広がる草地を縦横に使いながら、つい40年ほど前まで、このまちの真ん中で酪農が行われていたとは。最盛期の昭和37、8年頃、牛は42頭まで増えたという。
敷地の井戸水も搾乳には欠かせないものだった。「うちはいい井戸水が出てね、『酒づくりに売んねすかや』と言われたくらい。その水を毎朝4時半に起きて、沸かすことから仕事が始まる。牛のおっぱいを暖めたり、搾乳機を洗ったりするのに欠かせなかったね」。広瀬川の伏流水が、豊かな井戸水を育んだのだろう。写真の小屋の中には、いまもその井戸が大切に守られ水神様が祀られていた。
井戸ポンプ小屋