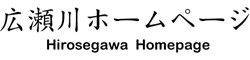■80歳をこえたいまも忘れ難い賢淵(かしこぶち)の思い出
加藤さんの話に出てきた「賢淵」で、思い出した人がいた。「仙台賢淵会」の青葉区在住大黒正さんである。戦前、盛んに賢淵で泳いだ河童たちが老境を迎え、川への思いやみがたく結成したこの会の会長さんを務められている。
久しぶりに伺うと、部屋の窓からは変わらず眼下に広瀬川が望め、涼やかな川風が入ってくる。大黒さんは83歳、いっしょに待っていてくださった嶺岸隆さんは79歳。お二人ともしっかりした体つきで、表情が明るい。賢淵は広瀬川の中でもとりわけ難所として知られたところだ。そこでの鍛練が体と気持ちを育んだのだろうか。
「はじめはメダカ捕りだよ。先輩が泳ぐのを見て、だんだん水に入るようになる、水に慣れてくるとガキ大将に深いところに連れていかれ手を放される(笑)。小学校2年生くらいになれば、みんな泳げるようになったもんだよ」と大黒さんが話し始める。「水に入る前に体操するのも、少しずつ体を濡らすのも、先輩がやるのを見よう見まねでね」と嶺岸さん。深いところや危ないところも、年長の子が教えた。だから、八幡町周辺の子で水の事故で亡くなった子はいなかったという。
「淵の深さは4~5メートルぐらい。飛び込みにちょうどいい岩もあったし、ツルが繁っていてぶら下がることもできたし、まぁ動物園のサルみたいに遊んだよ。5月末から入り始めて、夏はもう毎日だ」という嶺岸さんの話からは、子どもたちがカッパのように入り乱れ歓声を上げるようすが目に浮かんでくる。
大黒さんの家から望む広瀬川

昭和12年、淵を背に撮った写真には、小学校低学年から20歳代の若者まで、34人が写っている。この中の26名が、平成13年に会を結成し、一昨年には淵の上の道のわきに記念碑を立てた。
そこには、単なるなつかしさをこえた、もっと深い感情があるように思える。川との至福な一体感、川での体験が自分自身の根幹をつくったという感謝にも似た思いだ。
建立した記念碑

こうした川でのかけがえのない体験を、いまの子どもたちが持ち得ることはないのだろうか。菊地さんは「自分が川で経験したのと同じことを子どもたちに伝えたい」と話す。川の豊かさは、それを知る人が、次の世代へリレーしなければならないことなのだ。広瀬川は、同じように水をたたえ流れている。きっといまだって、かかわりの深さに応じた経験を、贈り物にしてくれるはずである。
淵の岩の上に神棚を安置する

賢淵で30年ぶりに泳ぐ