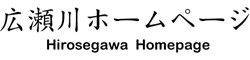くぐると、仙台市の名木・古木八十八選に選ばれた枝垂れ桜の古木があり、左からしぶきを上げて流れ落ちてくる沢に橋が架かっていた。社が造営された後の元禄時代の絵図を見ると、亀岡山には何本かの深い峡谷が描かれ、水は広瀬川へと流れ込んでいる。南から二本目の沢がこれだ。斜面に深く切り込んだ沢である。
鳥居わきの沢水

橋を渡ると、「輜重兵第二聯隊之碑」(しちょうへいだいにれんたいのひ)に目を引かれた。大きい。見上げるような記念碑に、関係した方たちの痛切な思いが見える。二ノ丸のあった川内一帯は、明治以降は第二師団指令部が置かれ、すべて軍の施設となった。中でも、兵器や弾薬、被服を戦地に運んだ輜重隊は、亀岡八幡宮に最も近いところにあった。戦勝祈願に多くの兵隊さんが参詣しただろう。武神だった八幡様には、いまも戦争の記憶が影を落とす。
その先には、石段がずっと上まで延びている。軍が近く狙われたのか、昭和20年の空襲で綱村建立の社殿は焼失し、鳥居と石段だけが往時をしのばせるものとなった。風雪に耐えてところどころ波打つ石段は、まるで崖のように険しい。亀岡八幡宮と大崎八幡宮を地形図で見比べると、参道の長さは大差がないが、標高は前者が約130メートル、後者が約80メートル。亀岡八幡宮は大崎八幡宮ばかりでなく、仙台城跡よりも高い位置にあるのだ。
息を切らしながら上る。くたびれて振り返ると、参道の黒い杉の間に白いビル街が輝いている。三千風や芭蕉は、この方角に宮城野を見たはずだ。350段ほどを上りきると、こじんまりとした拝殿が鎮座していた。あたりは静まり誰もいない。春の陽射しの下で入学祈願の絵馬が数枚、風に揺れていた。
街を見下ろす

さっそく小野さんの撮影地点を探すが、斜面には成長した樹木がスクリーンのように立ちはだかるばかり。広瀬川も望めない。木々のすきまから目を凝らすと、変わらないのは青い七つ森と大崎八幡宮の鎮守の森だけだった。
小野さんの撮影地点をさがす