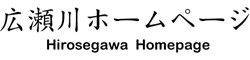■木橋のたもとにくり広げられた人情味あふれる暮らし
写真を見たとたん、千葉さんは「おぉ、なつかしい。昭和28、9年だね」と声をあげた。25年生まれの千葉さんは、この橋を眺めながら育った。昨年、この稿でいまにも崩れそうな木橋を取り上げたものの、結局どこの橋かわからずじまいだったのをご記憶だろうか(第1回目)。その橋も千葉さんは「間違いなく評定河原橋」と断定し、写真に写る堤防に掛けられたはしごをつたって河原に降りたことをなつかしがった。
白いズックの袋に早川牛乳をカチャカチャ鳴らし、まだ暗いうちから橋を渡って配達にきたのは“関のじっちゃん”だった。じっちゃんは木橋を「一銭橋」とよび、コンクリート橋になっても呼び方を変えなかった。動物園跡地には、ロマンとスリルがあった。「危ないから行くな」といわれても男の子たちは木橋を渡って出かけ、「ここでライオンだのヒョウが殺されたんだぞぉ」という年上の子の話を怖い思いで聞いていた。橋のたもとには東北大のラグビー部の学生を置く下宿屋があり、夕方になると学生たちは泥だらけになってグラウンドから上がってくる。話しかければにこやかで、ときおり相撲の相手もしてくれた。川は浅く、ドウを仕掛けると鰻がよくとれた。橋の下には、捨てられた子犬や子猫が流されてきて引っ掛かっている。かわいそうで拾って帰り、ご飯をやるようになった。何度もそんなことがあった。
片平丁にそびえ立つマンション群

だからこそ、「おまえは、評定河原橋の下で拾ってきた子だ」という親のおどしは現実味があった。「俺、しばらくの間、ほんとにそう思ってたもんねぇ」と千葉さんは笑うが、こんな説教が効いたのも子どもたちが川にさまざまなものが流れ着くことをよく知っていたからだろう。
昭和30年代の霊屋下の暮らしを活写する千葉さんの話は止まなかった。ときにはお米の貸し借りまでし、隣の子を自分の子と同じように面倒をみる生活がそこにはあったのだ。「やっぱりね、洪水の怖さとこの木橋で行き来するという不便さを、みんなで共有していたんだと思う。一体感というか団結力がすごかった」。それは、川に三方を囲まれた下町段丘ならではの暮らしだったのだと思える。こんな粗末な橋ではさぞや不便だったろう、という単純な見方を修正させられた気もした。
木橋から永久橋に替わり、平成6年にさらに立派に大きくなった橋のたもとには、いまどんな生活があるのだろうか。千葉さんが暮らしたあたりをたどってみたが、通りは静かで歩いている人にはだれも出会わなかった。その独特の地形ゆえに都市計画をまぬがれ、路地の入り組む親しみやすい雰囲気はそのままなのだけれど。
東北大グラウンド