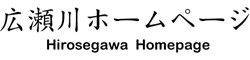フリーライター/西大立目祥子
広瀬橋上流付近(撮影/小野幹)

「ねぇ、子どもの頃見た長町の花火大会、楽しかったねぇ。通りに縁台出して、あたし、毎年おばあちゃんと並んで眺めてた」。太白区長町で育った友人が、久しぶりに里帰りしてなつかしそうに話していた。私も同じだ。もう40年近くも前なのに、花火大会の思い出は色あせない。いま、仙台の花火大会といえば、誰もが七夕前夜祭を思い浮かべるだろうが、昭和40年代の初めまでは、花火といえば長町、広瀬橋の上流だったのだ。
今回、小野幹さんが用意してくだった写真は、この花火大会のものである。
長い影から判断すると、夕方4時頃の広瀬川左岸。下流に見えるのが、昭和34年に架け替えられる前の広瀬橋だ。橋の上には人影も多く、堤防沿いでは神輿や幟を携えた祭りの出で立ちの人々が、いまかいまかと出番を待つ。そのわきではしゃぐ、提灯袖のワンピースの3人の女の子……打ち上げ前のざわめきが伝わってくる。当時を知る人を探して広瀬橋付近を歩いてみることにした。
■戦後始まった花火大会のにぎわい
昭和30年の花火

「戦後すぐの洪水の後、堤防が完成して花火大会が始まったのじゃなかったか。とすれば、写真は昭和30年前後」と指摘してくださったのは、長町で茶園を営む大竹誠一さんだ。「写真左側の竹を組んだのが五軒茶屋の裏の桟敷席ですよ。花火は郡山堰の下で上げたから、目の前に上がったわけだ。この頃の広瀬橋は電車と車が別々で、手前に見えるのが電車の鉄橋。花火のときは徐行運転してくれたもんですよ」。五軒茶屋というのは、藩政時代からの歴史のある料亭である。
河原町側、橋のたもとで生まれ育った高田つぎさんは、夫を戦争で亡くした後、6人の子どもをかかえて居酒屋を切り盛りし、毎年の花火の日を迎えた。「大工さんに毎年、桟敷席をつくってもらってね。なじみのお客さんがやってきて、枝豆、冷や麦、天ぷらにビールの特別メニュー。氷水も飛ぶように売れて、なくなると橋の向こう側の和田さんっていう氷屋に走って買いに行ったもんだった」。子どもたちも働いた。「花火は2日間で毎年のことだから、姉はいまでも一皿の値段まで覚えてる。私たちは花火なんて見てられないの。目に入るのは人の頭ばっかり」と、次女の松尾宏子さんも、休む暇なく手伝った当時を笑顔で振り返ってくれた。
小野さんの写真には続きの数枚があって、竹を組んだ桟敷席も写されている。「あら、桟敷席なつかしいねぇ!これ、枡席っていってね、1枡いくらで買ったのよ。私も買ってお得意さんご招待したわね」とは、河原町で呉服店を営んできた相澤さんの話。周辺の商店によるこうした利用のほか、桟敷席には銀行、デパートなど花火のスポンサーとなった企業のお偉いさんが招待されたらしい。
同じ地点から下流を見る

この花火大会が始まったのは、昭和27年のようだ(26年に開始とする資料もある)。仙台商工会議所と南仙台親交懇話会の共催で9月5日に開催。なんと花火は昼と夜の2回に分けて打ち上げられ、昼の花火には割引券などが盛り込まれたのだとか。その後、8月20日、21日となり、やがて17日、18日に落ち着いた。人出は昭和30年に、2夜で10万人を超えるまでになっている。
空に広がる大輪を、電車から料亭から桟敷から眺めて、同じように歓声を上げ、あたりが一つの空気に包まれる。当時を知る人の話からは、そんな雰囲気が伝わってくる。まだレジャーにも旅行にも出かけるゆとりはなかった時代、花火は誰もが心待ちにした夏の楽しみだったに違いない。高層ビルもマンションもない町の空は広く、頭上に高く高く大きな花が咲くのを見て、きっとみんな同じ夢を描いていたのだ。もっと豊かになろう、という夢を。