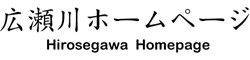■川に重ね見る江戸時代の大飢饉
大津波が沿岸部を襲っていたころ、私は宮沢橋を渡ろうとして車の長い列の中にいた。まさか、わずか5、6キロ先の地域を大津波が襲い、川をさかのぼっていることなど少しも疑わずに、余震に恐れながら川面を横目に見た。いったい誰が、川が大津波の通り道になると想像していただろう。がれきの破片は、郡山堰の近くまで流れ着いた、と聞く。
毎日のように宮沢橋と広瀬橋を渡り、橋の上から川を眺めて、特に晴天の日には胸がすくような遠望に心躍らせてきたけれど、3月11日の大震災以降は、広瀬川は心なごませる清流にとどまるものではなくなった。
暮らしが復旧していくのに反して、大津波の犠牲者は増え続ける。朝、新聞を開き、親子が、夫婦が、ときに家族全員と思われる人たちが犠牲になっているのを目にするうちに、私は、江戸時代の大飢饉の折、いまの広瀬橋近くの河原にお救い小屋が掛けられ、数千の飢えた人々が粥を求めて押しよせた姿をリアルに想像するようになった。
宝暦5~6年(1755~6)、天明3~4年(1783~4)、天保7~8年(1836~7)、仙台藩はたび重なる大飢饉に見舞われ、多くの領民が命を落としている。一粒の米もないやせ衰えた人々が、城下や周辺の農村から手を携えて河原に集まったのだ。
天明の飢饉では、途中、行き倒れになる者も多く、小屋までたどりついても一日に14、5人、多いときには50人を越える人々が命を落とし、まとめて埋葬して叢塚(くさむらづか)が立てられている。もはや一体ごとの埋葬は間に合わなかったのだろう。広瀬橋のたもとの桃源院に残る叢塚は、飢えのすさまじさをいまに伝えている。領内では、宝暦の飢饉で2万人、天明の飢饉で15万人から20万人の命が失われた。私たちは、おびただしい人の命が奪われた記憶を持つ土地の上に暮らしているのだ。
8月20日。毎年、宮沢橋の河川敷で行われる「広瀬川灯ろう流し」は、この供養に端を発している。この夏の灯籠流しは、屋台のテントと花火の打ち上げを待つ人、そして灯籠を流す人の長い列で立錐の余地もないほどだった。2万人に近い人が亡くなったのだから、肉親に加え、知人や友人を供養する人も少なくないのだろう。新盆の大きな灯籠を求める人の姿が目についた。
川面をすべりゆく灯籠

人垣を離れ川辺に立って、読経の響く中、暗い川の上をすべるように流れていく色とりどりの灯籠を見ていると、川はこの世とあの世をつなぐもの、と感じられてくる。そして、川は過去と現在をつなぎ、上流と下流を結ぶ。下流を望むとき、私は藤塚をはじめ大津波に襲われた地域の惨状と人々の顔を思い浮かべずにはいられない。