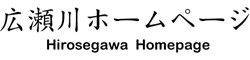■“鳴合の七つ石”で振り返る木流しの時代
石垣さんのお宅は、いまも大倉で石垣林業という会社を営み、光一朗さんで5代目になるという。一方、岡本さんの家は与惣治さんで3代目。おじいさんは、漆掻き職人で福井から宮城へ流れてきたのだそうだ。2つの家の接点は木流しだけだが、その背後には広瀬川上流に住み着いて、山の木を伐り、田畑を広げ、川と深くかかわりながら暮らしてきたいくつもの家族の物語が見えるようだ。
岡本さんの祖父は漆の仕事のかたわら、木賃宿も営んでいた。「七つ石の川原に温泉が出てて、旅の人なんかを泊めてたんだね。ここに上がってきたのは昭和10年頃だが、ばんつぁんは名残惜しくてちょくちょく川原にいってたよ。目の前が川だから、泳ぎはきびしく仕込まれた。淵の巻き込みがあるところにはいくな、石の下はくぐるな、ってね」。
岡本さんは、瀬や淵には名前があったといい、「柿崎にいくところのワタッパ、鳴合の大きな淵のカマフチ、柿崎橋の下のホソブチ」と、いくつかの名をあげてくれた。木流しの時代は、峡谷の細部、流れのそこ、ここを名づけなければ仕事にならなかったろう。
“鳴合七つ石”の川原

以前、案内していただいた“鳴合の七つ石”のことを聞いてみた。「クラカケ石、タタミ石、クジラ石、キノコ石、ミミズク石」と5つ上げたところで、ことばがとぎれた。これほど川に親しんできた岡本さんのような人でさえ、呼び習わす暮らしが遠ざかれば、その名を忘れてしまうのだろうか。
『宮城町史』では、この“鳴合の七つ石”を、鳳鳴四十八滝につぐ名勝として取り上げている。いま、その風景に親しむ人はどれぐらいいるだろう。
冬の合間の温かい日に川原に降りてみた。近くの家で下り口をたずねると「七つ石?まあ珍しい!」と、驚いた表情をされた。
40メートルほど急な斜面を下ると、ごろごろとした石がつくる川原の先に勢いよく水が流れ、踏ん張るように巨大な石が連なっていた。対岸からは岩盤を滝がすべり落ちてくる。自然の容赦ない営みを見せつけるような荒々しい光景だった。人の存在はいかにも小さいと思えてくる。
荒々しい川原の向こうに

この峡谷を雪解けの水が満たす頃、ごうごうと流れる水に乗って流木は一気にまちをめざし、それを祈るような思いで見下ろす親方がいた。そこに春の到来を感じる暮らしもあった。
木流しの時代が遠くに過ぎ去り、瀬や淵、石の名前が失われていく中で、広瀬川上流のこの深い峡谷に市民が関心を寄せることはもうないのだろうか。人工的に整えられた親水空間ではなく、人の手など及ばない川辺に立ってこそ、広瀬川は豊かに物語を語り出すように思う。
鳴合橋の上から

”鳴合の七ツ石”の名前 (『宮城町史 本編』より)
1.相逢石(あいおい)
2.松茸石(まつたけ)
3.鞍掛石(くらかけ)
4.臥牛石(がぎゅう)
5.起駒石(おきこま)
6.角鴟石(みみずく)
7.畳石(たたみ)
「相逢乃松茸石に鞍掛けて、臥牛起駒みみずくも 畳石とてやどるうれしさ」と、詩歌にも広く詠まれている。